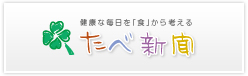健康のレシピ
お菓子のオカシな話
2011.11.09
お菓子(スイーツ)の歴史をたどってみると・・・
ケーキやチョコレート、ゼリー、ようかんやおまんじゅう・・・
現代、日常的に食べることが出来る甘い物の種類はさまざまです。 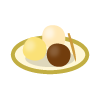
けれども砂糖がまだなかった大昔の日本では、甘味料は一般的に口に入る機会はありませんでした。
甘味は切望され、例えば甘蔓(あまづら)という蔓植物から採れる甘い樹液を煮詰めたものや蜂蜜が、ごく限られた人達に珍重されていました(「枕草子」にも登場)。
庶民にとっては、国内に自生する数少ない果物である柿やあけび、山ぶどう、栗などが「菓子」でした。
そしてその名残りが現代にも残っています。懐石料理等で、デザートに供される果物は「水菓子」と呼ばれています。
また、国内で本格的に製糖が始まる18世紀までは、砂糖はまだ貴重で滋養をつける「薬」として扱われていました。精製された白砂糖などは特に稀少な品でした(明治元年の1868年時点でも、米の約7倍の価格です!)。
舶来ものの菓子であるカステラも、薬としても扱われた記録があります。
そのため、ようやく庶民にも手が届くようになった頃には、砂糖は薬屋で薬種として扱われていました。
そして、砂糖が用いられた菓子が一般に販売されるようになった当初は、薬屋で菓子が販売されていました。
薬屋で菓子が扱われるようになった影響から、肉桂(シナモン)やなつめ、黄精など、薬種である原料や砂糖を材料とした菓子もつくられ、これは古くは「薬菓子」と呼ばれていました。
現在も各地でわずかにその名残が残っています(例:岩手県の黄精飴)。
健康のレシピ
- 2026.02.01ミキ薬局からのお知らせ
- 【2026年2月】ミキ薬局各店で栄養相談を行っています
- 2026.01.05ミキ薬局からのお知らせ
- 【2026年1月】ミキ薬局各店で栄養相談を行っています
- 2025.12.01ミキ薬局からのお知らせ
- 【2025年12月】ミキ薬局各店で栄養相談を行っています
- 2025.11.01ミキ薬局からのお知らせ
- 【2025年11月】ミキ薬局各店で栄養相談を行っています
- 2025.10.01ミキ薬局からのお知らせ
- 【2025年10月】ミキ薬局各店で栄養相談を行っています
- 2025.09.05健康のレシピ
- 【皮膚と栄養】915 防災とお肌の健康⑬ 糖質とビタミンB1
- 2025.09.04健康のレシピ
- 【皮膚と栄養】914 防災とお肌の健康⑫ 旬の食材
- 2025.09.01健康のレシピ
- 【皮膚と栄養】912 防災とお肌の健康⑩ 田端店 防災イベントのご案内
- 2025.09.01ミキ薬局からのお知らせ
- 【2025年9月】ミキ薬局各店で栄養相談を行っています
- 2025.08.29健康のレシピ
- 【皮膚と栄養】911 防災とお肌の健康⑨ 皮膚バリア機能の保持