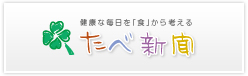健康のレシピ
日本の味覚⑧
2011.12.26
〜 苦味・えぐ味(山野草・野菜) 〜
生まれてすぐの赤ちゃんは、すでに糖質や脂質、アミノ酸などの甘味やうま味を好ましいと感じています。
これは、生きるために必要な熱量や栄養が豊富な食物の味であることを、生物として知っているためです。
逆に苦味やえぐ味は、植物などが外敵に食べられることを防ぐために身に帯びた刺激成分です。
小さな子供が苦瓜やピーマンを嫌うのは、当然のことです。
苦味やえぐ味は経験によって美味しく感じるようになる「大人の味」です。
特に日本人は四季の変化を、食物からも積極的に感じ取り、楽しもうとしました。
春先に芽吹く山野草は春の味覚として好まれました。
冬を越した体には、人にも動物にも、新鮮な植物の栄養は貴重です。
芽吹きのパワーと共に、この時期の山野草は無防備な若芽・若葉を守るための苦味やアクを持っています。 
食べたい、けれど苦い・・・。
日本人は、春先の植物の苦味には冬に溜まった毒を出す力があり、クスリになる、と考えるようになりました。
![]() そして、適度にアク抜きしたほろ苦さを、体に良いものとして好むようになりました。
そして、適度にアク抜きしたほろ苦さを、体に良いものとして好むようになりました。
この考え方は行事食にも反映されています。
七草粥は、正月のごちそうで疲れた胃を、あっさりした粥に早春に手に入る稀少な植物の力によって癒すために食べられました。
小豆粥は気を補う食物として、また赤い色に厄を祓う力があるとされ、小正月など寒さの厳しい時期に食べられました。
小豆は茹でこぼして渋切りをしますが、この渋(アク)成分(サポニン)が咳に働きかけるとして、現代でも薬膳などに用いられています。
植物にさまざまな力を見出そうとし、繊細かつ幅広い味覚を作り上げた先人の工夫を、あらためて見直したいものです。 
現代の野菜はアクが少なく、茹でたり水にさらすことでほとんど気にならなくなります。
苦味やえぐ味も野菜の持ち味です。
肉や魚と調理すると、これらの臭みを除き、味わいを深める組合せも多いです。
上手に付き合いましょう。
健康のレシピ
- 2026.02.01ミキ薬局からのお知らせ
- 【2026年2月】ミキ薬局各店で栄養相談を行っています
- 2026.01.05ミキ薬局からのお知らせ
- 【2026年1月】ミキ薬局各店で栄養相談を行っています
- 2025.12.01ミキ薬局からのお知らせ
- 【2025年12月】ミキ薬局各店で栄養相談を行っています
- 2025.11.01ミキ薬局からのお知らせ
- 【2025年11月】ミキ薬局各店で栄養相談を行っています
- 2025.10.01ミキ薬局からのお知らせ
- 【2025年10月】ミキ薬局各店で栄養相談を行っています
- 2025.09.05健康のレシピ
- 【皮膚と栄養】915 防災とお肌の健康⑬ 糖質とビタミンB1
- 2025.09.04健康のレシピ
- 【皮膚と栄養】914 防災とお肌の健康⑫ 旬の食材
- 2025.09.01健康のレシピ
- 【皮膚と栄養】912 防災とお肌の健康⑩ 田端店 防災イベントのご案内
- 2025.09.01ミキ薬局からのお知らせ
- 【2025年9月】ミキ薬局各店で栄養相談を行っています
- 2025.08.29健康のレシピ
- 【皮膚と栄養】911 防災とお肌の健康⑨ 皮膚バリア機能の保持