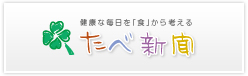健康のレシピ
行事食 No.18 花見
2012.03.05
桜に因むあれこれ
桜はヒマラヤ原産で、日本では万葉集に歌われたように古くから親しまれる花です。
何もない枝にパッと咲いていさぎよく散る姿や、繊細な桜色が愛でられました。
唐風文化が重んじられた頃は花の代表の座を梅に譲りましたが、国風文化が隆盛した頃から桜が復権します。
上流階級の間で行われていた花見は、時代を経るにつれて庶民の間にも浸透しました。
華やかに装い、花見酒や花見弁当を持って満開の桜の下に繰り出し、非日常の解放感を楽しみました。 
日本の桜は古くから改良が繰り返され、数百の種類が存在します。
ほとんどが観賞用ですが、大島桜の葉や、八重咲の種類の花は塩漬けにされ、桜餅や桜湯、餡パンのヘソの彩りに利用されます。
桜餅特有のあの甘い香りは、大島桜の葉に特に多く含まれるクマリンという芳香成分です。しかし大島桜を海外で栽培すると、その香りは弱くなるそうです。
桜餅は関西では道明寺粉を用いた粒々の餅、関西では小麦粉の皮で餡を挟むのが特徴です。葉を食べるかはずすかは、各人の好み次第です。
 花見団子は白、桜色、緑に染めた団子です。
花見団子は白、桜色、緑に染めた団子です。
これは冬、春、初夏の季節の移ろいを色で模したものとされます。
桜エビや桜マスはその色を桜色に例えたものです。
 なお、馬肉を「桜肉」と呼ぶ理由は、切り口が桜色だからという説には疑問があります。
なお、馬肉を「桜肉」と呼ぶ理由は、切り口が桜色だからという説には疑問があります。
現代では鮮やかな桜色の馬刺しにお目にかかることができますが、解体・鮮度保持の技術が未発達な時代には、肉の酸化による変色が強かったと考えられ、桜色の発想は難しかったと考えられます。
また、桜の咲く頃が馬肉の旬であるとの説は、「桜肉」というコトバを重視して「桜花」に掛けた可能性があります。
野生馬とは異なり、人の手で飼育・管理される食用馬の肉には、明確な旬の区分は無いようです。
肉食が忌避された時代にも、病後や寒中など、滋養強壮の目的であえて肉食をすることがありました(薬食い)。
このような場合、畜肉を直接呼ぶことを避けた都合上、馬肉が「桜」、鹿肉が「紅葉(もみじ)」、猪肉が「牡丹」呼び慣わされていました。
これらの語源は、
・鹿は秋の季語であるため紅葉に掛け、
・猪肉は色がそのとおり牡丹色
・馬は「咲いた桜に何故駒つなぐ」という古い俗謡の歌詞になぞらえた
という説が有力でとされています。
健康のレシピ
- 2026.02.01ミキ薬局からのお知らせ
- 【2026年2月】ミキ薬局各店で栄養相談を行っています
- 2026.01.05ミキ薬局からのお知らせ
- 【2026年1月】ミキ薬局各店で栄養相談を行っています
- 2025.12.01ミキ薬局からのお知らせ
- 【2025年12月】ミキ薬局各店で栄養相談を行っています
- 2025.11.01ミキ薬局からのお知らせ
- 【2025年11月】ミキ薬局各店で栄養相談を行っています
- 2025.10.01ミキ薬局からのお知らせ
- 【2025年10月】ミキ薬局各店で栄養相談を行っています
- 2025.09.05健康のレシピ
- 【皮膚と栄養】915 防災とお肌の健康⑬ 糖質とビタミンB1
- 2025.09.04健康のレシピ
- 【皮膚と栄養】914 防災とお肌の健康⑫ 旬の食材
- 2025.09.01健康のレシピ
- 【皮膚と栄養】912 防災とお肌の健康⑩ 田端店 防災イベントのご案内
- 2025.09.01ミキ薬局からのお知らせ
- 【2025年9月】ミキ薬局各店で栄養相談を行っています
- 2025.08.29健康のレシピ
- 【皮膚と栄養】911 防災とお肌の健康⑨ 皮膚バリア機能の保持