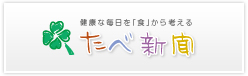健康のレシピ
刺身の日(8月15日)
2014.08.12
1448年(室町時代)の記録に、刺身という言葉が初めて記録に登場したのが、8月15日のため、この日が「刺身の日」と定められました。
「 魚の種類がわかるよう、その魚のひれを生魚の切身(なます)に刺しておくのが『刺身』の名の起こり」との記載が残されています。
「なます」は、新鮮な肉や魚を細長く切る調理でしたが、これは現在、切り身の「刺身」に変化し、現在なますといえば、大根やニンジンの細切りの酢の物がイメージされます。
記録が残されていた頃に尊ばれていた魚は鯛や鯉が主流で、鯛の刺身や鯉の洗いが代表的な刺身ではなかったかと考えられています。
醤油が普及するのは江戸時代中期になってからのため、梅酢や塩で刺身を賞味していたと考えられます。
大根やニンジンのなますに酢を用いるのは、古来より用いていた調味料(酢)の名残です。
現在、刺身といって思い浮かべるマグロはこのころは脂が強く傷み易い下魚(下賤な魚)とされていました。
このため、身分の高い(新鮮な魚を口にすることのできる)人々が、マグロを刺身なますとして食べることはありませんでした。
醤油が普及し、漬けマグロが寿司ネタとして庶民の口に入るようになるのが江戸時代中~後期。
生の新鮮なマグロが刺身の主役となるのは、冷凍・冷蔵・物流技術の発展した近代からです。
日本人の長い歴史の尺度の中では、伝統食と考えられていた刺身の発展は、ごくごく最近のことのようです。

健康のレシピ
- 2026.01.05ミキ薬局からのお知らせ
- 【2026年1月】ミキ薬局各店で栄養相談を行っています
- 2025.12.01ミキ薬局からのお知らせ
- 【2025年12月】ミキ薬局各店で栄養相談を行っています
- 2025.11.01ミキ薬局からのお知らせ
- 【2025年11月】ミキ薬局各店で栄養相談を行っています
- 2025.10.01ミキ薬局からのお知らせ
- 【2025年10月】ミキ薬局各店で栄養相談を行っています
- 2025.09.05健康のレシピ
- 【皮膚と栄養】915 防災とお肌の健康⑬ 糖質とビタミンB1
- 2025.09.04健康のレシピ
- 【皮膚と栄養】914 防災とお肌の健康⑫ 旬の食材
- 2025.09.01健康のレシピ
- 【皮膚と栄養】912 防災とお肌の健康⑩ 田端店 防災イベントのご案内
- 2025.09.01ミキ薬局からのお知らせ
- 【2025年9月】ミキ薬局各店で栄養相談を行っています
- 2025.08.29健康のレシピ
- 【皮膚と栄養】911 防災とお肌の健康⑨ 皮膚バリア機能の保持
- 2025.08.28健康のレシピ
- 【皮膚と栄養】910 防災とお肌の健康⑧ 食物繊維