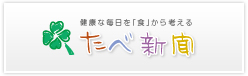健康のレシピ
旬の食べ物(157) 漬物
2012.11.26
漬物
漬物は生鮮品が乏しい時期をしのぐ保存食として発展を遂げました。
野菜だけではなく、魚の漬物(ぬか漬けやなれ鮨)、肉の漬物(味噌漬・
粕漬)なども作られました。
家族や地域で一冬を通して食べるため、樽(たる)にいくつという単位
で多量に漬け込み、熟成の経過も味わう事が出来ました。
塩漬・醤油漬・味噌漬・砂糖漬・油漬、酢漬・ぬか漬・麹漬・粕漬け等
があります。高菜漬けや柴漬けのように乳酸発酵による酸味のある漬物も
あります。
これらの漬物は調味料や漬け床による複合的な作用により
・調味量によって細菌やカビが利用できる水分を奪う
・重石や液体によって、素材に触れる酸素を減らす
・酸度を調整(乳酸発酵など)する
ことで、細菌の増殖や酸化が妨げられます。
また、素材の日干しや燻し(いぶし)、下漬け(あらかじめ塩漬けに
して水分量を減らす)、皮むきや切り方などの下処理も、保存性や風味、
食感に多様な変化をつけます。
冬の低温環境は、漬物をじっくり熟成させ、素材から特有の風味を引き
出します。
たとえば魚の漬物はタンパク質がじっくりと分解されることにより、
旨味成分のアミノ酸が作り出され美味しさが増してゆく代表例です。
(魚の塩蔵には、塩分に耐性のある菌による食中毒の危険があり、鮮度や衛生面に細心の
注意が払われました。)
また、糖質が多いために発酵がすすみ易く、酸っぱくなりがちな米麹や
甘味を用いた漬物も、冬に漬けることで甘味がじっくりと素材になじみ、
酸味を抑えてまとまりのある味わいに仕上げることができます。
現代では年中生鮮食品が入手できるため、漬物に保存性を求める必要
はなくなりました。
美味しさを追求し、少量ずつ、健康的に塩分控え目の漬物を作っては
いかがでしょう?
温度が一定の暗冷所が無い場合、冷蔵庫を利用するのもおすすめです。
健康のレシピ
- 2026.02.01ミキ薬局からのお知らせ
- 【2026年2月】ミキ薬局各店で栄養相談を行っています
- 2026.01.05ミキ薬局からのお知らせ
- 【2026年1月】ミキ薬局各店で栄養相談を行っています
- 2025.12.01ミキ薬局からのお知らせ
- 【2025年12月】ミキ薬局各店で栄養相談を行っています
- 2025.11.01ミキ薬局からのお知らせ
- 【2025年11月】ミキ薬局各店で栄養相談を行っています
- 2025.10.01ミキ薬局からのお知らせ
- 【2025年10月】ミキ薬局各店で栄養相談を行っています
- 2025.09.05健康のレシピ
- 【皮膚と栄養】915 防災とお肌の健康⑬ 糖質とビタミンB1
- 2025.09.04健康のレシピ
- 【皮膚と栄養】914 防災とお肌の健康⑫ 旬の食材
- 2025.09.01健康のレシピ
- 【皮膚と栄養】912 防災とお肌の健康⑩ 田端店 防災イベントのご案内
- 2025.09.01ミキ薬局からのお知らせ
- 【2025年9月】ミキ薬局各店で栄養相談を行っています
- 2025.08.29健康のレシピ
- 【皮膚と栄養】911 防災とお肌の健康⑨ 皮膚バリア機能の保持