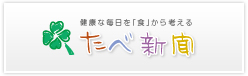健康のレシピ
行事食 No.43 油祝い・油しめ
2012.10.30
油を使った料理
日本で現在のように食用油が使用出来るようになったのは、さほど昔
の話ではありません。
油はほんの少量でも高い熱量を得ることが出来ます。
菜食が中心の昔の日本食において、庶民にとって大変貴重なエネル
ギー源でした。
けれども菜種や荏胡麻などの種子を絞って採取できる油の量は少なく、
日常的に使用出来る食品ではありませんでした。
また、庶民に比べ食事内容が厳しく戒律に縛られていたお寺では、限
られた食材から摂取出来るエネルギー量が更に不足します。僧侶の摂取
エネルギー確保と体力維持のため、貴重品ではあっても食用油の使用は
不可欠でした。
このように仏教と油料理には深い関わりがあります。
仏教は大陸文化の入口である都から国内に広まってゆきました。大陸
から渡来した油料理も仏教と共に国内に広まり、次第に日本風に工夫が
施されていゆきました。
![]() こうして雁擬(がんもどき:雁の肉に見立てた豆腐の揚物)
こうして雁擬(がんもどき:雁の肉に見立てた豆腐の揚物)
や具を油で炒めるけんちん汁などが作り出されました。
国の都には朝廷や貴族社会、寺社が集まります。
食用油のみならず灯火油も多く消費されるため、製油業は近畿から関
西地方を中心に発展を遂げました。
このため現在、関西地方を中心に油に関する食文化の季節行事が
残っています。
旧暦11月15日は 『油しめ』 『油祝い』です。
冬に備え、エネルギーの高い油を用いた料理を食べて体力をつける、
という行事です。
農家では菜種や荏胡麻(エゴマ)を自家栽培し、この日にその油を
絞って油を用いた料理を食べていました。
貴重な油を使った料理を食べることが出来る特別な日です。(地方に
よっては、この日は家事を担う女性達を上座に据え、その労をねぎらい
男達が油を用いた料理を作る例もあります)
現代ではこの日に天ぷらや餅、けんちん汁を沢山食べる風習が残って
いる地域があるようです。
けれども現代の食生活では油の摂り過ぎが問題視されることがしばし
ばです。
普段の食生活をかえりみて、『適量』を意識しましょう。
そして、当たり前に食用油が利用できる現代の環境に感謝しましょう。
健康のレシピ
- 2026.02.01ミキ薬局からのお知らせ
- 【2026年2月】ミキ薬局各店で栄養相談を行っています
- 2026.01.05ミキ薬局からのお知らせ
- 【2026年1月】ミキ薬局各店で栄養相談を行っています
- 2025.12.01ミキ薬局からのお知らせ
- 【2025年12月】ミキ薬局各店で栄養相談を行っています
- 2025.11.01ミキ薬局からのお知らせ
- 【2025年11月】ミキ薬局各店で栄養相談を行っています
- 2025.10.01ミキ薬局からのお知らせ
- 【2025年10月】ミキ薬局各店で栄養相談を行っています
- 2025.09.05健康のレシピ
- 【皮膚と栄養】915 防災とお肌の健康⑬ 糖質とビタミンB1
- 2025.09.04健康のレシピ
- 【皮膚と栄養】914 防災とお肌の健康⑫ 旬の食材
- 2025.09.01健康のレシピ
- 【皮膚と栄養】912 防災とお肌の健康⑩ 田端店 防災イベントのご案内
- 2025.09.01ミキ薬局からのお知らせ
- 【2025年9月】ミキ薬局各店で栄養相談を行っています
- 2025.08.29健康のレシピ
- 【皮膚と栄養】911 防災とお肌の健康⑨ 皮膚バリア機能の保持